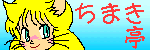愛・地球博
混雑の原因
会場の大混雑
愛知万博は、会場面積が173haあり、他の「半年2,000万人」クラスのイベントと比べると、かなり広めの会場になっています。しかし、その面積の半分は森のまま残されていて、会場としては機能していませんでした。
最初は入場者数2,500万人として計画された愛知万博は、その後の会場予定地の変更と森の保全を受けて、1,500万人の計画に変更されました。この1,500万人と言う数字は、おそらく会場面積から逆算された数字だったのではないかと思います。しかし、面積が少なくなっても人々の興味や関心には影響がないので、この辺にすでに大きな誤算があったのでしょう。
非常に多くの人が、この1,500万人すら達成出来ないだろうと予想していました。しかし、いざ開催してみると2,200万人が押しかけてしまう事となりました。前半が非常に低調で1,000万人すら難しいだろうと言われていたにもかかわらず、誰もが予想しなかった入場者数を記録してしまったのですから、後半の混雑のひどさは大変なものだったのがうなづけます。
元々1,500万人で計画されていたので、1日平均8万人、最混雑日でも15万人と見積もられていました。それなのに8〜9月は20万人を越えるのは当たり前、9月18日には28万人を記録してしまいました。結局それが、さまざまな方面に影響を与える事になってしまったのです。
各パビリオンも「入場者の○%が当館に来館」と言う仮定で計画を建てていたため、入場者数の目算がズレた分だけ大変な行列になってしまいました。
行き場を失った大勢の人達がグローバルループをさまよったため、グローバルトラムが邪魔な存在になってしまいました。
パビリオンや飲食やトイレや会場内交通もことごとくパンクしてしまいました。もちろん、会場外も大混乱。毎朝ゲート前広場から人があふれてしまいアーリーオープンが当たり前となり、どれだけ並んでも見れないパビリオンが多いために夜中のうちに来場して行列するのが当たり前になってしまいました。
以下に、これまでの日本での主な博覧会の入場者数をまとめてみました。
愛知万博の面積は、公式な面積の半分にしてあります。「単位当たり人数」は、入場者数÷日数÷会場面積で計算しました。
| 開催年 | イベント | 日数 | 入場者数 | 会場面積 | 単位当たり人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 大阪万博 | 183日 | 6,422万人 | 350ha | 1,003人 |
| 1985 | 筑波科学博 | 184日 | 2,033万人 | 101ha | 1,094人 |
| 1990 | 大阪花博 | 183日 | 2,312万人 | 105ha | 1,203人 |
| 2005 | 愛・地球博(計画) | 185日 | 1,500万人 | 86ha | 937人 |
| 2005 | 愛・地球博(実績) | 185日 | 2,204万人 | 86ha | 1,377人 |
愛知万博が計画通りなら、他の博覧会と同様な混雑で済んでいたはずだと言う事がわかります。
ちなみに、愛知万博の1日の最多入場者数は28万人で1ha当たり3,200人、大阪万博は83万人で1ha当たり2,400人になります。
パビリオンの大行列
愛知万博はパビリオンの混雑もひどいものでした。でも、かなり早くから「パビリオンの人気や面白さと、行列の長さには全く関連性がない」と言う事が言われていました。
行列の長さは、純粋に「時間当たりの入館可能人数」で決まっていたのです。ですから私もよく、初めて来場と言う人に出会うと「行列に並んでも中身を期待してはいけないよ」と言う事を教えていました。
中には「行列の長さがパビリオンの人気のバロメーターなんだ」と言う意識を持ち、どんどん行列を長くしてしまう見栄っ張りなパビリオンもあり、来場者にとっては迷惑で迷惑で仕方がありませんでした。(トヨタ、日立、韓国、ドイツ)(ドイツは自サイトで「70万人もの人が大行列を作ってまでも見に来てくれて大成功を収めた」と自画自賛している)
逆に、行列が短くなる様に最初から演目や建屋の設計に気を配っていたパビリオン(三菱、三井・東芝、JR)や、出来てしまった行列をどうやってもてなそうかと言う事にひたすら腐心していたパビリオン(JR、電力)もあり、この辺に顧客第一主義を大切にしている企業なのかそうでない企業なのかを垣間見る事が出来ました。
以下に、各パビリオンの入館者数をまとめてみました。
まずは、入館するのがとても難しかった企業パビリオンから。「朝いち入場してダッシュしなければ見れない」「3〜4時間は当たり前」なパビリオン達です。
| パビリオン | 入館者数 |
|---|---|
| ワンダーホイール展・覧・車 | 148万人 |
| 三井・東芝館 | 163万人 |
| 日立グループ館 | 170万人 |
| ガスパビリオン | 247万人 |
| トヨタグループ館 | 265万人 |
以上のパビリオンは、いずれも入館者数がとても少ないです。「行列長=単位時間入館可能人数」の関係があり、人気や面白さとは無関係だった事がわかります。
ワンダーホイール展・覧・車や三井・東芝館は、構造や演目の性質上、これ以上入館者数を増やすのは無理なので仕方ないのですが、その他のパビリオンは企画の段階からの工夫次第で、入館者数を増やす事は出来たはずです。
次いで、比較的入りやすかった企業パビリオンです。「長くても2時間以内」なパビリオン達です。
| パビリオン | 入館者数 |
|---|---|
| JR超電導リニア館 | 690万人 |
| ワンダーサーカス電力館 | 373万人 |
| 三菱未来館 | 303万人 |
JR超電導リニア館の数字は、ラボとシアターの合計の人数なのではないかと思います。それでも、単純に2で割っても345万人にもなります。
ワンダーサーカス電力館や三菱未来館は、企業パビリオンの中でも1〜2を争う大人気館でした。人気があるにもかかわらず、行列は極端に長くなる事はなく、比較的に入りやすかったです。
参考までに、入館者数を発表している外国パビリオンの数字も挙げておきます。
| パビリオン | 入館者数 | 混雑原因 |
|---|---|---|
| ドイツ館 | 70万人 | ライド |
| 北欧共同館 | 230万人 | 「メッセージを笹舟に書いて水に流す」コーナーで人が滞留 |
| カナダ館 | 330万人 | 映像展示 |
オース虎リア館 | 360万人 | 映像展示 |
| 中国館 | 566万人 | 特になし |
大行列で連日大混乱を引き起こしたドイツ館が、いかに入館者数が少なかったのかが、よくわかります。
ちなみに、入館制限しなければならない原因が何もなく、コンスタントに人が入り続けたとすると、入館者数は600万人程度になる様です。