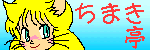献血未体験の方へご案内
献血ってなに?
献血とは、病気で輸血を必要としている人のために、元気な人が血を分けてあげるボランティアの事を言います。
血液は人間の臓器の一部。輸血すると言う事は臓器移植をすると言いかえる事もできます。その移植する血液はそのものズバリ「ナマモノ」で、とても高い鮮度が必要です。そのためどこかに血液を蓄えておくと言う事ができないのです。
交通事故で瀕死の重症を負った、病状が急に悪化して緊急手術する事となった。誰がいつなんどき、輸血が必要になるかわかりません。元気な人が元気な時に血をわけてあげて、輸血を必要とする人達を助ける、その善意の橋渡しが献血なのです。
なぜ、献血なのか
日本もその昔は、輸血に必要な血液は、血を売りたい人から買っていました。売血と言います。しかしこの売血、貧乏な人ほど血を売りたがるため、血液に病気が混ざっている確率が低くなくて問題になっていました。また、貧乏な人は繰り返し血を売りに来るために、どんどん血が薄くなってフラフラになって、それでもまだ血を売りに来る(「黄色い血」と言う言葉がありました)と言う問題もありました。そこで、血液はお金で買わない、ボランティアで血を分けてもらう、と言う事となったのです。1964年の事です。
献血の種類
献血にはおおまかに分けて2つの種類があります。血をそのまま抜く「全血献血」と、血の中のとある成分だけを分離して残りを返してもらえる「成分献血」です。
全血をそのまま輸血しなければならないのは緊急な時か特別なケースの事が多く、実際の輸血では患者の必要としている成分のみを輸血する場合の方が多いらしいのです。あと、血液から作るお薬も、血の全部を使うと言うわけではなく、うわずみだけを使って作られています。そこで考え出されたのが成分献血と言う献血方式だったのです。
血の全部を抜くのと違って、一部の成分を抜くだけなので、成分献血は全血献血と比べると、体にかかる負担はかなり小さいです。ただし「血を抜いて→分離して→血を返す」と言う事を繰り返す分だけ、ただ単に血を抜くだけの全血献血と比べると、ちょっと時間がかかってしまいます。
献血できる場所
街角で時々見かける献血バスの他に、都市になると常設の献血ルームと言うものがあります。
バスがいつどこに来るのかは、ポスターで見かける事も多いですが、市町村の広報なんかにもよく載っているので、チェックして下さい。ただしバスはたいがいは、全血献血の設備しか持っていない様です。
献血ルームの場所は、日本赤十字社のホームページでチェックしましょう。
所要時間は?
待ち時間がなかったとして、受付開始から休憩を終えて帰れるまで、全血献血で約15〜30分位、成分献血で約40〜60分位でしょうか?
たいていはちょっと待たされたりするので、30分〜1時間位見ておきましょう。
献血ができる人の条件
こう言う人なら血を抜いても大丈夫だろうと言う事で、献血できる人に基準がもうけられています。
- 年齢
-
満16歳以上で200ml献血が、満18歳以上で400ml献血と成分献血ができる様になります。
年齢の上限は、一応65歳になるまで…条件次第で上下する様です。 - 体重
-
女性の場合は、40kg以上で200ml献血と成分献血が、50kg以上で400ml献血ができます。
男性の場合は、45kg以上で200ml献血と成分献血が、50kg以上で400ml献血ができます。
献血会場には体重計もあるので、わからなかったらその場で計れます。 - 血圧
-
低血圧な人は血を抜くともっと血圧が低くなって危ないので、献血できません。最高血圧が90mmHg以上であればOKです。
高血圧な人はたいていが体調不良だったりするので、危なくて献血できません。最低血圧が100mHgを切っていればOKです。
会場でお医者さんが計ってくれます。 - 血の濃さ
- 血が薄い人はそれ以上血を抜くと危なくなるので、献血できません。会場で看護婦さんが計ってくれます。女性の3割は、この基準にひっかかって献血できない様な、高い基準です。
- お医者さんの判断
- ○×式の問診票に記入をして、お医者さんとお話して「体調は万全そうだね」と認めれもらえれば献血できます。お薬を飲んでいるとか、寝不足とか、朝ご飯を食べてないとかだと、ダメになる可能性が大です。
- 特別な病気にかかった事があるか
-
輸血を受ける患者さんの安全を確保するために、特別な病気にかかった事がある人や、かかっている可能性がゼロではない人(海外旅行をしたばかりの人とか、とある国に長く住んでいた人とか、援助交際や同性愛の経験がある人とか)は、献血できません。
エイズやC型肝炎はもちろんとして、狂牛病やヤコブ病なども入ります。輸血を受けた経験のある人もダメです。お医者さんが問診表でチェックします。 - 過去の献血の回数
- 抜かれた血が回復するまでには、ちょっと時間がかかります。そのため、前回の献血からどれだけ日数が経っているか、過去1年間でどれだけ献血しているかによって、制限が加えられます。献血が終わったら、窓口の人に「次はいつからできるの?」と聞いておく事をお忘れなく。